土を使った絵画に関しては、ドイツの風土が影響しています。こっちにきてから、地面を意識するようになって―自分が地面の上に立ってる、歩いてる、というのをすごく感じます。黒土は素材としても以前から好きだったこともあり、それがここに来てペインティングと融合しました。土を使って「生きろ」を描いて、ベタニエンという建物自体に開館当時のエネルギーをもう一度呼び起こしたいという想いがあり、ベタニエンの160年の歴史と「生きろ」プロジェクトの10年の歴史両方が、会場中央部分の絵画で融合しているというイメージです。
Q.会場では展示を熱心に観ている人が多かったように感じました。以前に行ったプロジェクトのドキュメント映像の中でも、多くの鑑賞者が鈴木さんに直接感想を述べていましたね。作品を通じて人と接することは、ご自身の中で重要なことですか?
A.もちろんそうです。このプロジェクトをやっていてすごく面白かったのが、たった一つの言葉を書き続けているだけで、世界中のいろんな人と出会っているということです。多くの人が、「生きろ」について自分の考えを述べてくれたり、「生きること」について話し合ったりもします。それぞれ異なるバックグラウンドを持っていて、受け止め方も違います。
僕は以前絵画をやっていて、その後、自分の身体を作品の中に取り入れていくようになったのですが、人形を置いてやるのと本物の人間がやるのとでは全く印象が違うんです。人間が持っているエネルギー、人間がやることに意味があると思ってます。大きな作品を作って、一定の期間展示をして終わりという方法も良いのですが、僕の場合は、僕が居続けて書き続けて、時にそこに来た人と話をしていくということが重要です。常に有機的な部分が含まれている点が、このプロジェクトの好きな部分。観せ方はミニマルかもしれないけど、非常に有機的で直接的なんです。僕自体がエネルギーをもらって書き続けている生き物なので、人と話をして、こう思ったとか、こう感じたとコメントをもらえるのは嬉しいです。自分の身体だけでいうと、エネルギーとしてもらったものを、エネルギーとして出していく感じです。
Q.展示パネルには「現代美術作品を作っているのではなく、何かスピリチュアルなものを生み出している」と書かれていましたが、それはどういう意味でしょう?
A. 自分が繰り返し書いている精神状態は、瞑想に近い。でも瞑想の為にやっているのではないです。アートがどうこうというより、僕は人間の創造性に興味があります。僕のパフォーマンスは、アートのカテゴリーさえ無い国でやっていると、頭のおかしい人が毎日何か書いている、と思う人もあるかもしれない。でもこれがアートだろうがアートでなかろうが、それは僕にとってたいした問題ではないです。それ以上に、僕がやっている行為を観た人が忘れなくて、例えば数年後にふと思い出したり、「もしかして彼がしたかったことはこういうことなのかな?」と感じたりというようなことがあれば、僕は充分にその人と関わりが持てている気がします。それは僕の考えるアート像に近いです。言葉で言うと、どうしても「アート」という言葉を使ってしまうし、やっぱり今回も展覧会ということ自体が、「アート」という枠の中に入った作業になっているので、どうしても「アート作品を発表します」という方法でしか言えないのだけど。絶対にこれをアートだと認めてほしいという気持ちは全くない。それよりも、スピリチュアルというか、わからないままでも伝わっていくということの方が僕に取っては大事。
「生きろ」と書かれた紙の束に囲まれて、ひたすら書き続ける彼の姿は、修行僧のようにも見える。がしかし、道徳を説くわけでもなく、ただその姿をさらし、紙を並べているだけだ。彼はなぜそれをしているのだろうか、彼は何を伝えようとしているのだろうか、「生きろ」とは何だろうか―そんなことを思わずにはいられなかった。仕事や日々の煩雑な出来事に追われ、毎日「生きている」にもかかわらず、「生きている」ことを実感すること無く過ごす私たちにこの言葉は、非常に鮮明な響きを持って心に飛び込んでくる。
人の心を揺さぶったり、得体の知れない何かを心に残す、それは「アート」が持つ魅力の一つである。「生きろ」と書き続ける彼の姿は、その力を持っている。
|
 |
 |
ベタニエンに関する資料展示の横で、真剣に鈴木さんを見つめる鑑賞者。

|
 |
10年分の「生きろ」プロジェクトのドキュメント資料が並ぶ

|
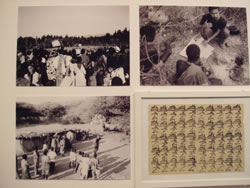 |
1998年にタンザニアで行なった時の記録。

|
 |
オランダで行った展覧会のドキュメント映像。この時は、鑑賞者と話しがしやすいよう、ブースを設けた。

|
 |
絵画作品

|
|