
 |
 |
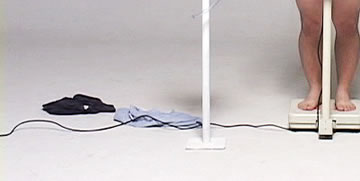 |
 |
| �^�����T�g���u100kgMan�v2004�N |
|
�f����i�����[�����키���߂�
TEXT ���i���j
�͂��߂�
�Ⴆ�A��x�f��قŌ����f����ォ��Ƃ̃e���r�Ō���ƁA��ۂ��ς���Č�����A�Ƃ������Ƃ�����B
�f���͊G��⒤���ƈقȂ�A�X�N���[����j�^�[�ɉf���o���Ă͂��߂Ċӏ܂��邱�Ƃ��ł���B���̍ۂɂǂ̂悤�Ȋ��ŏ�f����邩�ō�i�̈�ۂ͑傫���ς���Ă��܂��B
���̓_�ŁA���́w�s�N�`���[�E�C���E���[�V����DeLuxe�x�͂ǂ��Ȃ̂��B
��f������i�́A������20�����A�Z�����̂͂P�b���邩�Ȃ������炢�̉f�������[�v���Â����i�ł���A������J��Ԃ��J��Ԃ���f����Ƃ����B
�ʏ�̓W����ł���A���̂悤�ȏ�f���@���Ƃ�̂ł���A�X�N���[���Ȃ胂�j�^�[�Ȃ��ʁX�ɗp�ӂ��Ă����āA�ʁX�̃u�[�X�ŏ�f���邾�낤�B��ʂ̑O�ɂ͂�����Ƃ����x���`�ł��u���Ă����āA�ӏ҂͎v���v���Ƀx���`�ɍ������肠�邢�͗������܂܂Ō����肷��킯���B
�������A�w�s�N�`���[�E�C���E���[�V����DeLuxe�x�̉��ƂȂ�W��́A���ׂ�ꂽ�֎q(�������őO��̓\�t�@�[�I)�ɑ傫�ȃX�e�[�W�A�����ăX�e�[�W����ɂ���傫�ȃX�N���[���A�Ƃ��Ȃ���P���Ԃ���Q���Ԃ̊Ԃ�������ƍ��𗎂������ĉf����ӏ܂��邩�̂悤�Ȃ����ނ����B
�܂��A���ꂼ��̍�i�ɂ��Ă�1��������f�����A��f���͈�̍�i���������͂P�������X�Ə�f��������Ƃ����B
�����Ɍ������B
�l�͍ŏ��A����ȏ�f�X�^�C���ɁA�u�Ȃ�ł���ȏ�f�̂�����������낤�H�v�ƈ�a�����o�����ɂ����Ȃ������B
�������A��i���������Ă��邤���ɁA���̏�f�X�^�C���Ȃ�ł͂̌��ʂ�Ӑ}���������悤�ȋC�������B
���ꂪ���Ȃ̂����A��i���Ƃɍl���Ă݂����B
����q�b�uKOJIMA�v�̏ꍇ
��ʒ����ɂ́A�������Ƃ����������f���o����A���̂܂��������������Ă����B
�����������Ă����ɂ�A�����̘e����A�ɉB��邪�A��������Ɣ��Α����猻���B�����āA�����̖T��ʼn��ɂȂ��Ă��炭�x�ނƁA�܂������̂܂�����������̂��J��Ԃ��B
�J�����͂����ƌŒ肳�ꂽ�܂܂ŁA�X�e�[�W�̌���ɉf���o����邱�Ƃɂ��A�������X�e�[�W�̃Z�b�g�̂悤�ɂ������A���̂܂������ۂ̏��������X�Ƃ܂�葱���Ă���悤�Ɍ�����B
�܂��A�������Ƃ��������͂܂�Ő��E�̂悤�Ɍ����A���̂܂����܂�葱���鏗�����l�������g�̐l���Əd�Ȃ��Č����Ă���̂��B

�c�����N�u123456�v2003�N |
�c�����N�u123456�v�̏ꍇ
��ʂɂ͑傫���O���X���f���o����A���̒��ŃT�C�R�������B
��]�̉f���̓��[�v����A�~�܂邱�ƂȂ����X�Ɖ�葱����B
�������Ă��������ɁA�O���X�̒��ŃT�C�R�����`���O�Ղɖڂ�D���A����ƂƂ��ɋK���I�ɋ�����]�̉����������Ɏc��B
���ܖڂɂ��Ă���T�C�R���̉�]�̘A���́A�f���̕ҏW�ɂ���Đl�דI�ɂ���ꂽ���̂Ȃ̂ɁA�܂�ł��ꂪ���R�̐ۗ��ł��邩�̂悤�ȕs�v�c�ȃ��A���e�B��ттĂ���B
�����āA���ʂł��̉�]�̘A�����������邱�Ƃɂ��A��������]�̉Q�Ɋ������܂ꂽ���̂悤�ȗՏꊴ�𖡂키�̂��B
�s�ӂɃu���u�����Ɛg�̂�������Ă��܂��قǂɁB
�����֎q�u������̋L���v�̏ꍇ
��ʂɂ͌��̔��Ƃ�����Ȃő�����肪�A�b�v�ʼnf��B
�ŏ��͌������킢�����ĂȂłĂ���悤�ɂ������邪�A�������Ă��邤���ɁA�l�q�������������ƂɋC�Â��B
�����҂���Ƃ������Ȃ����A�ȂłĂ������A�܂�Ō��̊��G���m���߁A��Ɋo�����܂��悤�Ƃ��Ă��邩�̂悤���B
���ꂪ���ʂʼnf���o����邱�Ƃɂ��A�܂�Ŏ��������ۂɌ����ȂłĂ��邩�̂悤�ȗՏꊴ�𖡂키�B
�����Ă����ƌ��i�߂Ă����ƁA���̊炪�f���o����A���łɎ���ł��邱�ƂɋC�Â��B
�����̎肪���ڎ��ɐG��Ă��܂����悤�ȁg���̎�G��h�����������ŁA���ꂪ�J��Ԃ���f����邱�ƂŁA�����̘A������̏z�Ƃ����������I�Ȏ��_�������A��胊�A���e�B�������Ă���悤�Ɏv�����B
���ׂĂ͐��E�����[�����키���߂�
���̂R��i�Ƃ����ʂ��Ċ������̂́A��i�������E��Z���Ɋ��������Ƃ��B
�@���ʂ́A�f����S�g�ő̊����邽�߂�
�@�[���֎q�ɍ��|��������̂́A���𗎂������Đ��ʂ����i�ƌ������������߂�
�@���[�v����f���́A��i��S�Ɛg�̂ɐ[�����ݍ��ނ��߂�
�@�e��i�̏�f��1���Ɍ���̂́A��i�̃��A���e�B��[�߂邽�߂�
��i�̏�f�ɂ��Ă̂�����v�f����i��[�����키���߂ɍ�p���Ă���Ɗ�����B
�����Ă݂�w�s�N�`���[�E�C���E���[�V����DeLuxe�x���̂��u���̉f����i�̐��E�����[�����키���߂̎��݁v�ł���A�Ђ��Ắu�l�����̏Z�ނ��̐��E�����[���������邽�߂̎��݁v�Ƃ�������B
���ꂪ��i������x�X�g�̕��@���ǂ����́A�c�_�̗]�n�����邾�낤�B
�������A�f�������X�ɏ����Ă͏����Ă������݂ɂ����ẮA���̎��݂͑����̎����ɕx��ł���悤�Ɏv����B
�s�N�`���[�E�C���E���[�V����DeLuxe
�Ȗ،������p��(�Ȗ،�)
2005�N11��3���i�E�j�j�A11��5��(�y)�A11��19��(�y)�A12��3��(�y)�A12��17���i�y�j
|
|
�@ |
���҃v���t�B�[����A�ߋ��ȂǁB
���i���j�i�悱�Ȃ��������j
1972�N�Ȗ،����܂�B
2002�N�́u�Ƃ������ی���A�[�g�W�w�f���[�e���x�v�����Č�����p�ɋ��������B
���݂́A�̋��œ����Ȃ���A���Ԃ����Ĕ��p�ق�M�������[�ɒʂ����X�B |
|

|