|
|
|
�u�쑺�m�v�̐��E��W�]����
TEXT �����`�V
|
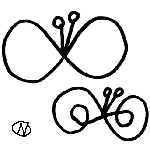 |
|
|
| �@ |
�@�����V���p�قɂĊJ�Â��ꂽ�u �쑺�m�@�ω����鑊�|���E��E�g���v�W�������B�쑺�Ƃ����_���{�[���ƃh���C�A�C�X��i���v���o����邪�A����̓W�������đz������L���͈͂ɋy��ł���̂ɋ����A�傫�ȕϖe�Ԃ�Ɋ������邱�Ƃ����������B���܂�ɂ����@���G�[�V�����������̂ł��ׂĂ��Ƃ炦�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�����ł͂��̒��ň�ۂɎc������i�����Ă��������B
|
�@ |

�쑺�m�@�sTardiology�t1968-1969�N
|
| �@ |
�u�����̑��v
�@����Ƃ����傫�Ȓi�{�[������4�i�A���������ς��ɐςݏd�˂��Ă����B����8���[�g���̓V��قڂ��ꂷ��ł���B1969�N�ɐ��삵����i��Tar��iology��
�̍Đ���ł���B�����쑺�́u���v�����Ԃ̌o�߂ƂƂ��Ɍ`��ς��Ă����l�q���ʐ^�ɎB��A�u�d�́v��u���ԁv��ڂɌ�����`�ŕ\�������B�ςݏd�˂��_���{�[���������Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɕ���Ă����l�q���B���������̎ʐ^���W������Ă����B1969�N�Ƃ����܂��Ɂu���̔h�v���o�ꂵ�����ł���B�u���̔h�v�́u���v����i�̑f�ނƂ��Ďg���̂ł͂Ȃ�����Ƃ��ēo�ꂳ���A�u���v�̂���悤��₤���B�쑺�͂��̔h�Ƃ͕ʂ̎��_����u���v�������̂ł��낤�B���̎������̔h�ƕʂ̎��_�Ƃ͐����B�h���C�A�C�X��i��Dryice:1969����������̂��̂ł���A���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɏ����`�̕ς���Ă����l�q���ʐ^�ŕ\������Ă����B�����͖쑺�̏����̍�i�ł��낤�B
|
|
�@ |
| �@ |
�@ |
�u�n��̑��v
�@�u���v����쑺�̎v�l�͎������g�̂���u�n��v�ւƐi�B�f����i��J��������Ɏ����r���F�l���A���i��(1972)�͂��̈��ł���B�t�B�����E�J������Ў�ɘr��t��������܂킵�A�J�����̑�������i����i�ɂ����B�\�Ȍ���u�n��v��S�e�����B�J�����̎ʂ����f���͎v�������Ȃ�����̕��i�ł���B�t���܂ɂȂ������Ǝv���ƕʂ̕��i���f��ȂǏu���ɑ�����i�������B�g�̂Ǝ���̊��i�n��j�Ƃ̊W������ȕ��@�ŋL�^�����B�J�������Ƃ炦���u�n��v�̎p�͖쑺�̈Ӑ}�������̂�������������Ȃ��B
�@�܂��A�쑺�͐����ɕ��V��������q�������N�����s�K���ȉ^���u �u���E���^���v�ɒ��ڂ��A�����̓��������l�ƍl���u��������̂��ׂĂ��ʂ��v�^�������s����B���ꂪ�c��Ȏ����ƂȂ��i�ɔ��f���ꂽ�B���̍l�����͖쑺�ɂƂ��ďd�v�ȃ|�C���g�ɂȂ�悤�ł���B
|
�@ |

|
 |
�u�V��̑��v
�@�u�n��v����쑺�̎v�l�͈ꌩ���Ăǂ���Ȃ��u�V��v�ւƔ��W�����B�u�u���E���^���v�̈�̐��ʂł��낤�B
�@���z�⌎�͎��Ԃ̌o�߂ƂƂ��Ɉړ�����B�쑺�͑��z�⌎�̓�����ǐՂ��Ă����Ɉ��̑f���炵�������̂��邱�Ƃ����o�����B���̋K���I�ȓ������Ƃ炦���y�I�\�������݂��̂ł���B�t�B������5�{�̐����ʂ�����Ō����B�e�����̓����������ɂ����B��i��'moon'
score��(1975-79)������ł���B���y�����ɗ���Ă����B�����������S�n�悢���y�������B
�@�܂��A�k��35�x�ɂ�����1�N�Ԃ̑��z�̋O�Ղ�����������i����k��35�x�̑��z��(1982-87)�ł���B�����ꏊ����������Y�t���J�����̃V���b�^�[���J�����Ė����̓������B��1�N�ԑ��������̂ł���B���ׂĂ̎ʐ^�����̓����ɉ����ĕ��ׂĂ݂�Ɠ��ɂ��̌o�߂ƂƂ��ɖ�����L�����̂悤�ɂȂ����̂ł���B�ĂƓ~�͉~�`��`���A�t�ƏH�͓�������������B�S�e����ƌ����ȍ�i�ƂȂ��Ă����B |
| �@ |
�@��A�i�����}��V���[�Y���������B����I�ɓ����ꏊ�����莞�Ԃɑ��z�̈ʒu��1�N�Ԏʐ^�ɎB�葱���A���̓�������i�ɂ������̂ł���B���z�̋O�Ղ͌����ȂW�̎��i�����j�X�P�[�g���A��`�j��`���Ă����B��ߑO�̃A�i�����}�90��A�ᐳ�߂̃A�i�����}�90��A��ߌ�̃A�i�����}�90��(1990)�̓W���B���߂̍�i�͐�����8�̎���`���f���炵����i�ɕϐg���Ă����B
�@�����͖쑺���u���v����X�^�[�g���u�n��v�A�u�V��v�ւƎv�l�W���������ʓ���ꂽ���̂ł���A���R�̒����A�@�������o���A�����������ɂƂ炦�����z�͋����ق��Ȃ������B |
| �@ |
��j�쑺�m�@�s�k��35�x�̑��z�t�@1982-1987�N�@���s�s���p�ّ�
���j�쑺�m�@�s���߂̃A�i�����} �f90�t�@1990�N�@�a�̎R�����ߑ���p�ّ�
|
|
�@ |

|
| �@ |
�u�F���̑��v
�@�u�V��v���猩�����⑾�z�̓������Ƃ炦���쑺�́u�F���v�ɂ܂Ŏv�l�W�����Ă����B�F���̐����A�`�Ԃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂���쑺�͊ώ@�ɂ���č�i�ɔ��f�������B
�@COWARA�́ACosmic Waves & Radiation�i�d���g�ƕ��ˁj�̗��B��i��COWARA��(1987-92)�́A�F��������˂����d���g�𑨂����̔g�������ɕϊ����ăX�s�[�J�[�ŕ������u�ł���B�����ɃX�s�[�J�[���������u����Ă����B
�@�܂��A�F���̐����ƌ`�Ԃ������ł���悤�K���X�Ő��삵�Ă����B��i��^��̔�����(1989)�͖쑺�̍l����F���̎p���낤�B��������Ƃ��낾�B�������̌E�݂̓u���b�N�z�[����������Ȃ��B�ł��F�����Ă���Ȋi�D���낤���H�K���X�ŕ\�������͖̂ʔ��������B�@ |
| �@ |
�@���̂ق�覐��o�ꂵ�Ă����B�n����̐����̋N����覐���������Ă��������ł���B覐̏Փ˂ɂ���ėL�@���q����������A�����Ő�����DNA���`�����ꂽ�Ƃ��B覐�DNA�͌^�̓W���ȂljȊw�I����ɂ܂ő��Ղ��L�тĂ����B
|
| �@ |
��j�쑺�m�@�s�^��̔����t�@1989�N�@���s�����ߑ���p�ّ�
���j�쑺�m�@�sCosmo-Arbor �f06�t�@1999-2006�N
|
 |
�u���Â̑��v
�@�u�F���v�͉�X���l���鎞�Ԃ̊ϔO�ł͓���Ƃ炦���Ȃ��B���N�̐��E�ł���B�Ⴆ��1��5000���N�O(�W�����I)�ɔ��������������̒n���ɓ͂��Ă���̂��B���̓����̒n����̐����͍��ł͉��̐��E���B��i��1000���N�̐ڂ�����(2000-2007)���W������Ă����B��̉������݂̑���ɂ�����ɐڂ��������̂ł���B������ɂ��Ă��̏�ɉ��̑�ߍ��ނ悤�ɍڂ��������ł���B�Ȃ����f���炵����i�ƂȂ��Ă����B�F�A�`�A���������҂����莗�����Ă������炾�낤�B
�@�܂��A��i��W�����I�̋��F�L����(1998-2000)�́A���̉��̓W���Ɣw��̕ǖʂɒn�}���\���Ă������B�L���Ŕ������ꂽ���̂��낤�B�������̑�����݂܂Ő��炵�Ă�����ǂ��Ȃ��Ă��邩�B���������ł���B�N�ւ�1�~�����B�L���𒆐S�Ƃ��Ĕ��a200�L�����[�g���̑�ƂȂ��Ă��邻���ł���A�n�}��ɉ~�`��`��������Ă����B�ߋE�n���������ۂ�����Ă��܂��B����������������������s���Ȃ��������낤�B���{�̗��j���ς���Ă������낤�B�ƂĂ��Ȃ����z�Ŗʔ����B����ȍl�����ی��Ȃ�����ꂽ�B
|
|
�@ |

��j�쑺�m�@�s�T���X�g���N�`���[
�f99�t�@1998-1999�N
���j�A������ތ��ꖔ�́e���Ƃ��Ă���f������
|
| �@ |
�u�����̑��v
�@�v�l�́u�ߋ��v�����]���u�����v�ɂ��L�����Ă������B�������v�l�����낢��Ȓ�Ă����Ă���悤�ł���B�P�̓\�[���[�J�[�̐���ƃA�����J�嗤�̉��f�ł���B�����ł̃\�[���[�J�[����o������ɁA�\�[���[�J�[��T���X�g���N�`���[�f
99��(1998-99)�𐧍�B�A�����J�嗤���f�̃v���W�F�N�g�𗧂��グ�A1�J�������ăA�����J���C�݂��瓌�C�݂܂ő��s�����B���̃\�[���[�J�[��T���X�g���N�`���[�f
99�₪�W������Ă����B
�@�܂��A�����Ɍ���������Ƃ��̕����̐����ɉ���������̔g���݂̂����˂���F�Ƃ��ĔF�������B���镨������ɂ��������X�y�N�g��������ƕ����ɂ��F�̔z�قȂ�g���������ł��邻���ł���B�������琶�܂ꂽ�̂��o�[�R�[�h�������r�������悤�ȐF�ʖL���ȍ�i��Chromatist
Painting��ł���A���_���W������Ă����B
�@�A�����Ȃ̂͗��z�������ɔ��˂��邩��ł��낤�B�A���ɂ��낢��ȐF�̌����Ǝ˂��A�ǂ�ȐF�ɐA�����������邩�̎����R�[�i�[���������B���낢��̐A�����K���X�P�[�X�̒��ɒu����A����ނ��̂��ꂢ�ȐF�̌����F�ʂɐA���ɓ��Ă��Ă����B���̎������炢�낢�땪���邩������Ȃ��B���̂悤�ȐA���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����͖ʔ������ʂ�����ꂻ���ł���B
�@�ȏゲ���ȒP�ɖ쑺�̕����Ղ����ǂ��Ă݂��B�l���̋y�Ȃ��L�����E���o�ꂵ�ڂ܂��邵���ς��l�q�����邱�Ƃ��ł����B�쑺�̎v�l�̍L������ɂ킽���Ă���̂����ċ�������Ȃ������B���܂�Ƃ����m��Ȃ���M�̂Ȃ���킴���낤�B������y���݂ł���B�܂��A���̍L�͈͂ɋy�ԓ�����e����₷���������Ƃ���W�����悩�����B��������������p�W�������B
|
| �@ |
|
|
 |
| �@ |
�@ |
���҃v���t�B�[����A�ߋ��ȂǁB
�����`�V
1934�N���A�����ی���ЋΖ��A�ސE���ʌ����ߑ���p�قɂă{�����e�B�A�����Ƃ��ăT�|�[�^�[(��ݓW������i�K�C�h)���s���B
�E�G�u�T�C�g�@ART.WALKING
�E�A�[�g�ɓ��������R
���g�O���t�w�����_�@�A���̌㌻����p�ɂ��S�����B
�E�D���ȍ�ƂT�l�ق�
��i���D���Ƃ������A���������ƁB
�N�[���x�A�}�l�A�Z�U���k�A�s�J�\�A�f���V�����A�|���b�N�A�E�H�[�z���ȂǁB |

�@
|
�@ |
�@ |