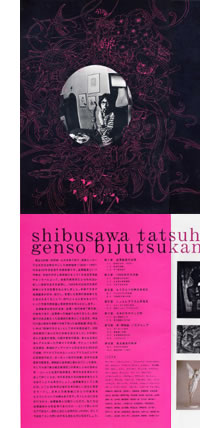 |
 埼玉県立近代美術館で《渋澤龍彦―幻想美術館》展が開催された。《シュルリアリスム展》に続く開催である。この美術展も楽しみだった。両美術展を通してシュルレアリスムをいろいろな角度から見ることができた。 埼玉県立近代美術館で《渋澤龍彦―幻想美術館》展が開催された。《シュルリアリスム展》に続く開催である。この美術展も楽しみだった。両美術展を通してシュルレアリスムをいろいろな角度から見ることができた。
渋澤龍彦(1928〜1987)といえば作家・批評家・仏文学者であり、美術エッセーでも知られている。彼のエッセー(《幻想の画廊から》、《幻想の彼方へ》いずれも河出文庫)を読むと独特のシュルレアリスム論が展開されていて面白いし参考になる。シュルレアリスムというと美術史上では、エルンスト、マグリット、デルボー、ミロ、ダリなどが挙げられているが、渋澤の場合はそれに留まらなかった。ルネッサンス期から20世紀までそれも日本の画家を含めてであり、この美術展もかなり広範囲の展示だった。
巌谷国士の著書に《シュルレアリスムとは何か》(ちくま学芸文庫)がある。この本によると、(「」内、巌谷国士の著書から)
「・・・、便宜上大きく分けると、シュルレアリスムの美術は二つの道をとるようになります。・・・『自動デッサン』の流れがひとつ。そして、デュシャン、エルンスト以来ひろがっていったもうひとつの流れに、『デペイズマン』の方向があるでしょう。・・・」(注)
「・・オートマティックなデッサンを日本で実行していったのが瀧口修造です。」
「渋澤さんは1950年代からシュルレアリスムを盛んに称揚するようになっていたわけで、・・・、瀧口さんのようなオートマティスムを核心とする『シュルレアリスム』とはちがう、『デペイズマン』経由のシュルレアリスムです。」
「瀧口修造のほうは、特にジョアン・ミロを中心に彼のシュルレアリスム美術論を展開していきました。」
「渋澤さんは、シュルレアリスムの美術をかなり広範囲に捉えていて、・・・彼の取り上げた画家を見ると、ミロには一言も触れていないし、1960年代にはデュシャンのことも、マン・レイのことも語っていない。渋澤さんは、見て何なのかすぐに分かるいわゆる具象的な絵しか取り上げなかったともいえます。」
|
 |