|
カルチャー・ショック
TEXT 菅原義之
|
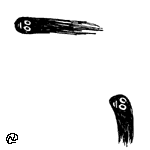 |
以前のことだが、4月21日は私のガイドの日だった。2時3〜4分前に常設展示室に行った。お客様は7、8名おられた。
まず、さいたま市出身の画家“高田誠”のコーナーからスタートした。
油彩9点の概略を説明した。高田の絵は点描法をとるが、新印象派のスーラ、シニャックの点描とは違うなどもあわせて話した。お客様はそれなりに関心を示していた。
次のコーナーはいわゆる“現代の美術”のコーナーであった。
このコーナーに入ったとたんに薄笑いしている二人連れの女性がいた。あとで分かったことだが、その時はなんと不思議なものかという笑いのようであった。
内容は主に“もの派”の作品が多く展示してあったといっていいであろう。
そこで「美術というと何を思い出しますか。」と2〜3の人に聞いた。
お客様の一人が、小声で、「絵ですか。それと彫刻なども」という。
引き続き次のように話した。
戦後、美術は大きく変わり、その範囲を急速に広げていった。したがって美術をこれまでのように“絵画”、“彫刻”と考えるととてもついていけない。
この部屋には、1960年代以降大きく変わった考え方の中で活躍した作家の作品が展示されている。この傾向は日本だけでなく、世界的に展開されていった、と。
まず、高松次郎の『布の弛み』から始めた。
これまでの表現方法にとらわれない独特の見方を作品に導入した作家であると断った上で、この作品は、大きな四角い布が床に置かれている。本来フラットに置かれるべきだ(=感ずること)が、中央部分が膨らんでいて何か変だと思う(=実際)。つまり“感ずること=認識”と“実際=見ること”の“ずれ”を強調している。
これだけでは分かりにくいと思い、あわせて『影のシリーズ』も写真を示して同様に話した。結果はどうであったか。何人かは面白いという素振りだった。
次は、かの有名な関根伸夫の『位相―大地』(写真展示)である。
1968年(昭和43年)に神戸の須磨離宮公園で野外彫刻展が行われた。そのときの作品である。直径2.2メートル、深さ2.7メートルの円柱状の穴を掘り、その脇に掘った土を利用して同形の円柱を作った。この作品を見たほとんどの人たちは、あまりにも衝撃的な作品に感動したそうである。残念ながら現在は埋めてしまって写真で見る以外に方法はないが、実物を今見ることができたらやはり大変な衝撃を受けるのではないか。賛同が聞かれた。
|